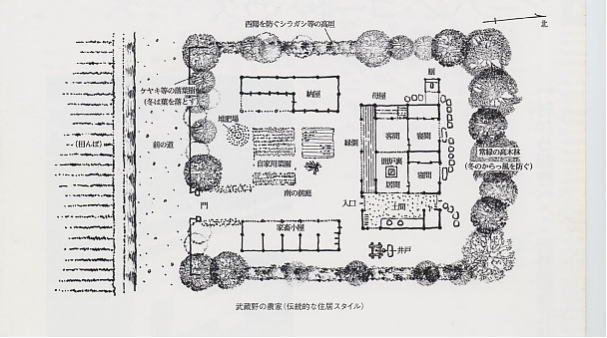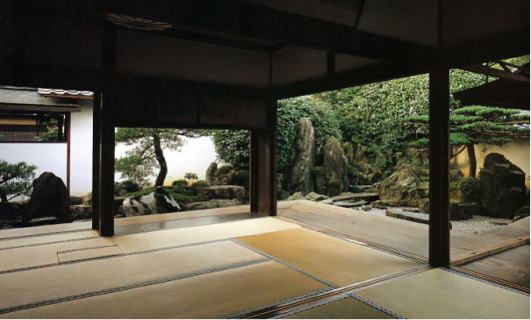【①話.簡単だけど大事なこと!】
【②話.日本人の「庭」感覚のルーツ】
【③話.都市化する農村住宅・・・「家」を囲う「塀」】
【④話.塀のない家・・・オークパークの住宅】
【⑤話.「塀の家」と「フェンスの家」】
【⑥話.和風住宅の「塀」の内側は・・・】
【⑦話.外の部屋?・・竜安寺/石庭】
【⑧話.狭小の外の部屋?・・大自然を取り込む最小庭園・・坪庭】
【⑨話.現代の住宅・・・塀がフェンスになって来た!】
【①話.簡単だけど大事なこと!】

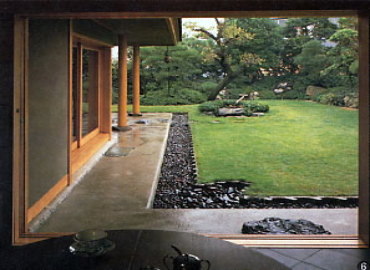
住宅を作り続けて30年・・・家づくりを始めた頃の、素朴な疑問から始まった私の建築論のお話です。
街を歩くと・・・・「家」本体には、いろいろな要望を注ぎ込んで造ったうと思える、かなり凝った作りの家であるのに、
「家」の外廻りは、まるであきらめてしまったような建て方の「家」が目立ちます。
「夢の庭付き一戸建て!!」・・・大金を掛けて新築するというのに・・・
一般の新築住宅に、「なかなかいいなあ」・・・と思える庭が無い。・・・何故だろう?
・・・・・いろいろ考えるうちに、あるとき「アレッ」と思うことに気づきました。
簡単だけど大事なこと!!
| 塀・・・と・・・フェンス |
庭・・・と・・・ガーデニング |
この似て非なるもの・・・この上の言葉の違いは何だろう?
簡単なことですが、私にとっては大事な疑問でした。
この十数年で・・・
「塀」が「フェンス」になってきた・・・同じ「囲い」なのに何処が違うの? |
「庭」が「ガーデニング」になってきた・・・同じ「庭」なのに何処が違うの? |
簡単に言うと左が漢字で右側がカタカナ?・・・ある意味で正解ですが・・・
この答えは私の建築創りの転機となりました。
私があれこれ考えた事をお話しいたします。